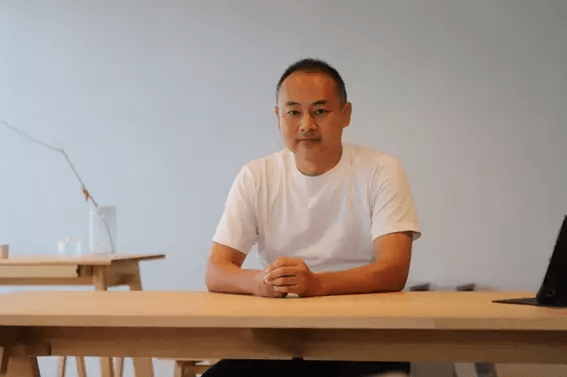周囲の色を映してしまう白の特質
~グレーを選んだきっかけ~
僕は近年、自分がデザインした空間の内壁にグレー系統の塗装をよく使っています。以前は白を随分使っていましたが、あまり使わなくなりました。なぜかというと、何回も使ううちに、まっ白、グレーがかった白、その中間ぐらいしか選択肢がないことに不自由さを感じ始めたのが一つです。もう一つは、白く塗った壁に昼間は床材の色が、夕方は照明の色が反射して壁に映るのが、あまりきれいだと感じなくなったからです。そこで他の色が使えないかと思い、4~5年前から、白に黄色や緑を入れたり、グレーやベージュを試したりするようになりました。

余計な色を拾わないグレー
僕がグレーを多用するようになったきっかけは、2019年にオープンした「dotcom space Tokyo(以下「dotcom」)」というカフェ兼イベントスペースのデザインの仕事でした。
多目的な空間にしたいという要望があったので、余計な色を拾わないピュアな空間を目指し、全体的にグレーのトーンで囲み、展示空間のニュートラルな“白い箱”のイメージを、実際にはグレーで表現しました。クライアントは「グレーが邪魔するのでは」と心配したようですが、アプローチを兼ねた大きな開口からの光も手伝って、実際に足を運んだ方々の多くは白だと認識してくれているようで、まさに僕の狙いが的中した形となりました。結果的に、この仕事が僕にとっての突破口になりました。

心地よさと学びのある空間
建築やインテリアのデザインは、“空間体験”を提供する技術だと思っています。空間を整えれば、光がきれいに入り、置かれてある家具もさらに良く見えます。そして“空間体験”に欠かせないのは、ほどよい緊張感です。僕が考えるほどよい緊張感とは、単なる心地よさだけではなく、学びがあり空間そのものに「こうありたい」と思わせる何かがあるということです。
そのために、大事にしているのは“ノイズ”を減らすことです。
たとえば、高級な温泉旅館でも、インテリアがうるさくて「落ち着きたい」「くつろぎたい」といった気持ちになれなかったら、せっかくの旅が台無しです。
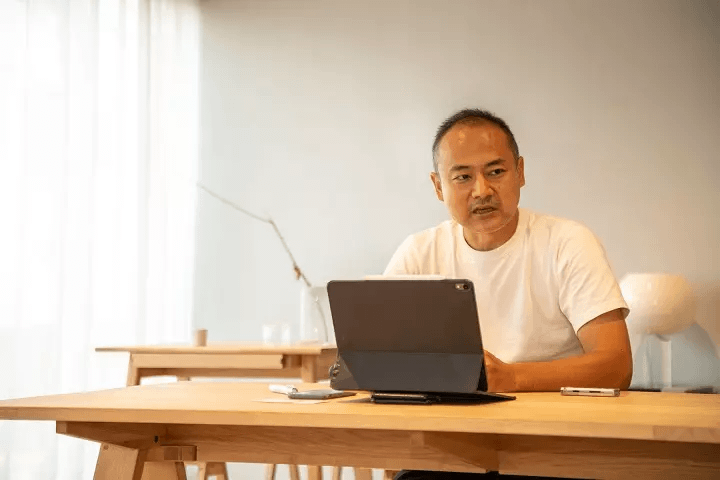
「Karimoku Commons Tokyo」にて。
環境全体への眼差しが空間を変える
もう一つ大事なのは“環境”全体で考えることです。
僕が言う“環境”は、いわゆる自然環境や建築の外部空間とは、捉え方が少し違います。その考えが生まれたのは、オーストラリアの建築家、ピーター・スタッチベリーさんの「Wall House」(2009年)という日本のプロジェクトを2年半ぐらい共働した時です。
プロジェクトに携わる間、ピーターさんの建築を一緒に巡り、ピーターさんと対話する中で、僕は“環境”という言葉に、私たちの身の回りにある建築や室内、外部など全ての空間が含まれていることに気付かされました。たとえばピーターさんのスケッチは、どこまでが部屋の中でどこまでが外側か分かりません。それは今思えば、彼が建築だけではなく、言うなれば“環境”全体をつくろうとしていることの表れだったのです。
壁の色が室内空間の調整役
ピーターさんのスケッチは、室内も重要な“環境”の一つであると教えてくれました。そこでカギとなってくるのが壁の色です。
壁の色は室内の雰囲気に強い影響を及ぼすので、僕は先に決めることはしません。まず周囲の状況に対して、何色が適しているか検討し、その結論として壁の色を導き出すのです。グレーを多用しているのは、あくまでも結果に過ぎません。
つまり僕は壁の色を、室内空間を構成する家具や床といった諸要素がきれいなハーモニーを奏でるための調整役として捉えているのです。その役割を果たすには、色の選択が自由自在な塗装が最も適しているというわけです。
(ポートレート撮影: 渡部立也)